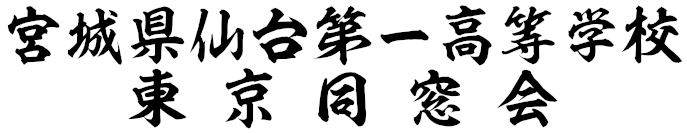2025年10月25日(土)、恒例の仙台一高東京同窓会の総会が東京都港区の芝パークホテルで開催されました。総勢140名が参加し、学生も15名が参加しました。
第一部は、定刻の11時に池上岳彦(高30回)幹事と鎌形真咲(高74回)幹事の司会で開会宣言が行われました。男女によるダブル司会は、総会初の試みでした。

その後、この1年にご逝去された東京同窓会元会員の皆さまのご冥福をお祈りし、黙祷を捧げました。
開会の挨拶

本間洋・東京同窓会会長(高27回)より開会の挨拶。
「本日の総会には、おかげさまで約140名の皆さまにご参加いただいております。今年の東京同窓会の活動についてご報告いたします。14名の現役幹事と世話役の皆さんが一丸となって、イベントなどを積極的に推進してまいりました。私も学生部会と校外研修に参加いたしましたが、仙台一高の仲間が世代を超えてつながり、本音でアドバイスを交わすことの意義を改めて感じました。学生の皆さんにとっても、得るものが多かったことと思います。最近特に「ご縁の大切さ」を強く感じております。人と人がご縁によってつながり、新たなエネルギーが生まれる。これは本当にありがたいことだと思います。おかげさまで、仙台一高東京同窓会の世話役は現在93名となっております。世話役がいない年次は、現在わずか2年次のみです。ちなみに第46回生と第57回生が該当します。来年にはゼロにしたいと思っております。これも、文武両道の仙台一高を愛してやまない仲間が多いということの表れではないでしょうか。また、東京同窓会の活発さは、創立130年の伝統を大切にし続けてきた結果であり、「自発・能動」の精神がエネルギーとなっているのだと思います。これからも、仙台一高の仲間とのご縁を大切にしながら、活動を続けてまいりたいと思います。私、本間はこの3年間、会長を務めさせていただきました。
今は少しほっとしておりますが、この間、皆さまには大変お世話になりました。本当にありがとうございました。」
母校近況のご報告

続いて、母校の樽野幸義校長から母校の近況をご報告いただきました。
「令和7年度の卒業者、高校80回生は、男子186名、女子175名、計361名となります。3学年全体で見ると、男子が約55%、女子が45%の比率で卒業します。
一高・二高定期戦では、軟式野球が4連覇、硬式野球が5連覇しております。硬式野球で6連覇は初のことですので、来年ぜひ達成したいものです。柔道の定期戦ですが、柔道部は不戦勝でした。これはどういうことかというと、本校に部員が1人なのですが、相手校に部員がおらず不戦勝になったのです。なかなか柔道部は今、部員集めに苦労しているところでございます。県総体の報告としては、ヨット部、ボート部、陸上部、水泳部、弓道部など幾つもの部がインターハイに進出しております。皆様ご存知かもしれませんが、ヨット部の3年生男子生徒2名が、日本代表としてトルコで行われた世界大会に出場してまいりました。先輩方からは多大なるご支援をいただき、この場を借りて改めて感謝申し上げたいと思います。
今年の夏の甲子園県予選ですが、本校野球部は準決勝まで進みました。準決勝で残念ながら仙台育英に負けてしまったのですが、仙台育英は甲子園で優勝した沖縄尚学に負けましたので、そこに負けた本校は「実質ベスト3かな」と、私は勝手な解釈をしております。
今年も一高祭(文化祭)が、8月30日、31日の2日間行われました。幸い天候にも恵まれ、7,000人を超える方々にご覧いただけたということでございます。
最近、熊の出没のニュースが全国的にもございますが、宮城でも同様で、残念ながら、その熊の危険性を鑑み、今年で60回目を予定していた強歩大会を中止せざるを得なくなりました。学校の行事を中止にしただけなのに、テレビ局2社、新聞社2社の取材があったことです。さすがにマスコミの報道を受けるということは全く想定していなかったので、そちらの対応の方が大変でした。
最後になりますが、9月段階での進路希望調査では、現3年生、78回生の希望を取ったところ、東京の大学を希望している者が92名おります。その92名が全員、来年東京に来ることを期待しておりますので、その節は先輩方、どうぞよろしくお願いしたいと思います。東京同窓会のますますの発展と会員の皆様方のご健勝をご祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。」
仙台一中・一高同窓会会長よりご挨拶

その後、仙台一中一高同窓会の佐浦弘一会長(高33回)からご挨拶をいただきました。
「本日は、令和7年度の東京同窓会の総会開催、誠におめでとうございます。そして、また、ご招待をいただきまして、心より御礼申し上げます。
同窓会のことで申し上げますと、今年の8月15日、毎年の恒例となりました大納涼大会は、53回生の皆様方が幹事学年で、580名を超える同窓生に参加していただき、無事盛大に開催することができました。また、この東京同窓会の皆様方からも、多大なるご支援をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。おそらく、また本日は、来年8月15日の大納涼大会のPRに、54回生がご出席をしてPRをさせていただくと思います。ぜひ皆様も、8月15日、お盆の期間ではありますけれども、ご参加をいただいて、大納涼大会にご出席をいただければと思います。
ところで、その強歩大会ですけれども、昭和41年から開催されているということで、本日ご出席いただいているちょうど高校20回生の先輩方の頃から開催された行事であると伺っております。時代は、70年安保の前夜ということで、仙台一高にも様々な動きがあり、生徒会の解散、制服自由化等、激動の時代でした。そのような時に、仙台一高の標語である「自発能動」を表現するようなイベントができないものかと、生徒主導で始まったのが、この強歩大会であると聞いております。今後、熊の出没が落ち着くのかどうか分かりませんが、ぜひその生徒主導で開催するこの強歩大会を山の方のルートでなくても、何か別の方法で準備対策をしていただいて、その伝統の灯をともし続けていただけないものか、切に願っているところであります。
先ほど、今年3月に入学したのが高80回生というお話がありました。男女共学になったのが高校65回生から。それから既に15代に渡り、共学の新入生を迎え、仙台一高の校風もその時代とともに変化し、全て同じという訳にはいきません。どのようにすればこの仙台一高魂を保持し、その一高らしさの伝統・校風を維持発展することができるのか、正に先輩方の力が必要ではないかなと考えております。私も同窓会会長になりまして、様々な集会、あるいは職員の会合に出席をいたしました。どちらの会合でもやはり出席される若い世代の皆さんが少なくなってきていることを危惧されています。同窓会の会合に出てくるのが、どのようなメリットがあるのか、あるいはどうしたら出やすい環境を作れるのかということを、これからますますしっかりと考えていかなければならないと思っております。
この東京同窓会の様々なその運営の方法、あるいは多くの人々が出席していただく、そういう仕組みというのは、非常に他の同窓会の会でも参考になることですし、もちろんそれは本部に取っても同じことだと思っております。今後どのように同窓会を運営していって、その同窓会の目的である、親睦はもちろんのこと、伝統・校風の発展に寄与できるかということについてしっかりとまた取り組んでいきたいと思っておりますので、先輩の皆さん、そして後輩の皆さん方にも、色々と同窓会の会合に出席をしていただいて、一高らしさをぜひ、今後、新しい世代の皆さんに伝えていっていただきたいと思っております。この東京同窓会におかれましては、学生部会や校外研修など様々な年間行事をしっかりと管理運営されており、見習いたいと考えています。
今後とも、是非、仙台一中一高同窓会の活動にご協力・ご支援賜りますと共に、今後の発展にもお力添えをいただきたいと思います。本日はおめでとうございます。」
決議事項・活動報告


会計報告を沢田博史(高33回)幹事から、監査報告を目黒憲一(高27回)監事から報告しました。続いて駒津敏行(高30回)幹事長からは、千葉光太郎(高28回)新会長を含む新幹事6名を迎えた14名の新体制について報告し、承認をいただきました。
千葉新会長よりご挨拶

代表して千葉新会長からご挨拶をいただきました。
「皆さん、こんにちは。28回、千葉光太郎と申します。私が入学したのは、入学が昭和48年、その当時は、学生運動が盛んな時期でありまして、先生方もあまり問題を起こして欲しくないということで、あまり強いことは言われなかったんですね。残念ながら、修学旅行はありませんでした。山小屋に行って、辛い思いをしたという記憶がございます。私は卒業後、浪人して、仙台の大学で5年間、機械を学び、日本鋼管という会社に入りました。鉄の会社だったんですが、配属されたところが、船の修理をするところで、そこに長年勤め、2回ほど合併・統合を経験しました。IHI、日立造船、日本鋼管、住友の造船部門が集まった ジャパン マリンユナイテッド(Japan Marine United)という会社で5年間ほど社長を勤めました。
今は退任して顧問という形で、日本造船工業会というところで副会長をやっております。皆さんも最近気になっていると思いますが、造船が非常に注目されておりまして、忙しくしております。「アメリカに造船所を作りたいのでアドバイスしてくれないか」という話も来ております。
今回、会長という大役を引き継ぎさせていただくにあたりまして、非常に迷ったのですが、大変名誉なことだと思い、引き継ぎさせていただくことにしました。やはり仙台一高を卒業したことで、私の人生における人間形成に非常に大きい影響を与えていただいた3年間だと思っております。
何が影響を与える要因だったのかなと改めて今回考えてみたところ、一つ思ったのは、やはり先生方に少なからず影響を受けていると思いました。土足のままで、ゴミだらけの教室を生徒が何やら大義を叫ぶ中、担任の先生が一人で掃除してくださっていました。「高校の教師なんかになるものじゃないよ」という愚痴を漏らされた数学の先生。当時、水俣病問題が取り上げられていましたので、授業の中に水俣病の事実を伝え続けてくれた加藤先生。それから、学校に反発して、卒業式に出ず、自主卒業式というのを生徒が勝手にやって、それに付き合ってくださっていた倫理社会の先生。
こういった先生方に我々は温かく見守っていただいて、それでぬくぬくと3年間を過ごしたんだなと。それがすごい影響を与えてもらえたのだとしみじみ感じております。
そのような訳で、一高を私自身も非常に強く愛しております。これから3年間、会長ということで努めさせていただきますけども、その中で、世代を横断し、若い世代の方にもどんどん来ていただけるような会にして行きたいと思っております。
新役員、また引き続き継続してくださる役員の皆さん、一緒に頑張っていきたいと思いますので、皆さんのご支援の程、よろしくお願いいたします。」
活動報告
活動報告では、駒津幹事長から交流会イベントや運営改善事項の報告があり、その後、関 基陽(高44回)幹事から、学生部会や校外研修等のイベントを報告し、この1年間の活動を振り返りました。
ハラスメント防止宣言について
母校が男女共学になり、この会も女性会員が、大勢参加されるようになってきており、世間一般でのハラスメント相談件数も増加していることを受け、今回の宣言を役員会として決定しましたので、総会の決議に諮り、承認されました。
原文は、規定にも掲げましたので、一読するとともにハラスメントのない同窓会運営にご協力をお願いいたします。
▶ ハラスメント防止宣言(PDF形式)
記念講演

講師 佐伯 一麦(高30回)氏
作家・仙台文学館 館長(3代目)
雑誌記者、電気工など様々な職に就きながら、1984年「木を接ぐ」で「海燕」新人文学賞を受賞し、作家デビュー。1990年『ショート・サーキット』で野間文芸新人賞、1991年『ア・ルース・ボーイ』で三島由紀夫賞、1997年『遠き山に日は落ちて』で木山捷平文学賞、2004年『鉄塔家族』で大佛次郎賞、2007年『ノルゲ Norge』で野間文芸賞、2014年『還れぬ家』で毎日芸術賞、『渡良瀬』で伊藤整文学賞、2020年『山海記』で芸術選奨文部科学大臣賞を、それぞれ受賞。他に『雛の棲家』『一輪』『木の一族』『石の肺』『ピロティ』『誰かがそれを』『光の闇』『麦主義者の小説論』『空にみずうみ』『アスベストス』『ミチノオク』など著書多数。
「作家生活40年を迎えて」と題して、今までの苦難や乗り越えた想い出を様々なエピソードを交えて、ユーモアとウィットに富んだお話をいただきました。最後には、あの菅原文太先輩からご本人が受けた助言と期待についての音声録音もご披露いただき、非常に感慨深い時間となりました。
※詳細は、著作権上の問題より割愛させていただきます。
第二部・懇親会
第一部の終了が25分も押したにも関わらず、ホテル側のスピーディーな対応のお陰で、定刻の13:15に第二部の懇親会がスタートしました。

第二部の司会は駒津幹事長と鎌形幹事が務め、開始挨拶の後、合唱部OBの住潔先輩(高20回)の先導により、仙台一高の校歌を斉唱しました。


最年長先輩による乾杯。
今年は、針生宏先輩(高6回)にお願いしました。遂に自分の番が来てしまったとおっしゃりながらも、元気に、声高らかに乾杯の音頭を取っていただきました。(最年少参加者は77回ですので、年の差はなんと71歳!
大納涼大会の報告と来年のPR
しばし歓談後に恒例の大納涼大会のPR。
佐々木大さん・佐野遊馬さん(高53回)より、今年の実施報告をしてもらいました。

第68回大納涼大会 ー 動員状況 ー
(2025.8.15 ホテルメトロポリタン仙台)
総チケット枚数 626枚
(前年比+200枚)
当日参加者数 583名
若手・高63回以降の参加者が100名と前年より倍増
続いて来年の幹事学年である高54回の三田将さんと田中素浩さんに来年の大納涼大会のPRをしてもらいました。
学生会員紹介

今年は、昨年の9名を上回り、15名の学生会員が参加し、それぞれ高校時代の部活や趣味を語っていただいた後、就職希望先の業種・業態をアピールしてもらいました。今後の就職の一助になれば幸いです。頑張れ!
東京同窓会総会・懇親会の華である「応援歌斉唱」!

幹事&元応援団松浦さん(高31回)の誘導のもと、初代女性応援団長の鎌形真咲さん(高74回)、と応援団OBの掛け声のもとで、応援歌1番、続いて、凱歌二番を熱唱しました。
皆様それぞれの勝利の思いに酔いしれました。ありがとう。
総会の参加者総数は140名。楽しいひと時もあっという間に過ぎ、定刻15:00に無事閉会しました。
老若男女の様々な同窓との新たなご縁と絆が生まれたのであれば、幸いです。
来年、2026年10月24日(土)に、場所も同じ芝パークホテルのこの会場でお会いしましょう。
文責:駒津敏行(高30回)